『都市型直売所の可能性を探る』8~農業集団も追求力の時代へ~ |
メイン
2014年12月08日
微生物と植物の協働関係を進化史から探る~農法の変遷と今後の可能性~

画像はこちらからお借りしました。
有機農法や、自然農法とは、農薬や化学肥料に頼らず、太陽・水・土地・そこに生物など自然の恵みを生かした農法です。消費者にとっては何となく安心、安全、体に良さそう、自然環境に良いなどのプラスのイメージを持っていることが多いと思います。
一方、農家側にとっては化学農法に比べて成長も遅く、収量が少ない、人の手で雑草、害虫対策を行わなければならず手間が掛かるというマイナスのイメージも多いことかと思います。
そこで今回は、元々は有機農法、自然農法からスタートした農業がなぜ化学農法に移行したのか?の歴史的な流れを押さえた上で、今後の農法の可能性追求している記事がるいネットにありましたので紹介したいと思います。
近代農法・有機農法・自然農法はどれも重要より。
画像はこちらからお借りしました。古くから野菜や穀物を育てる土壌には養分として、山林や原野の野草、人畜の糞尿、マメ科植物の緑肥が使われてきた。人類は、もともと自然農法や有機農法を自然に実践してきたといえる。それが19世紀に入り、産業革命が起きると急激に人口が増加し、食料供給の不安が起きるようになった。またこの時期、飢饉がヨーロッパを襲い、食料の安定供給が急務となる状況が発生したため、化学の世界で肥料の開発が進むことになった。
1840年、ドイツの化学者リービッヒが、無機栄養で植物が生育することを明らかにし、化学肥料の基礎理論を作ると、その後、彼のチッソ・リン酸・カリの3要素説に基づき、1843年にイギリスで過リン酸石灰の生産が開始。その後、遅れること70年、1913年にドイツでアンモニア合成工業が成功。チッソ肥料の大量生産から小麦の増産が可能になり、世界人口を急激に増加させた要因になったとされる。
人為的なアンモニア合成は、現在の地球の生態系における最大の窒素固定源となっているが、同時にこのアンモニア合成技術は、爆薬の原料となる硝酸の大量生産も可能にするものだったため、「平時には肥料、戦時には火薬を空気から作る」と形容される。人口を大幅に増加させた技術は、同時に人口を大量削減できる技術でもあった。
さて、現在では近代農業による化学肥料の大量使用から窒素化合物が土壌から大量に流出し、地球の生態系へ悪影響を与えることが懸念されており、また化学肥料で作られた農産物に含まれる栄養素の乏しさや過剰な硝酸態窒素が人体の健康面に与えるマイナス面から、有機農法、自然農法による農産物の生産が再び注目を集めている。細かく分類すれば種々あるが、大まかにいえば、西洋ではオーガニック、日本では有機農法と呼ばれる。
画像はこちらからお借りしました。
ここで、有機農法と近代農業の違いを区別するために近代農業で使用される化学肥料の定義を説明する。化学肥料とは、化学的工程を使い無機質原料から作られた肥料であり、現在、使われる肥料の大部分を占める。尿素や緩効性肥料は有機化合物だが、化学的工程で作られるものは、すべて化学肥料と呼ばれる。また塩化カリウムのように掘り出された鉱石を粉砕しただけで、化学的工程を経ないものも無機質原料であるため化学肥料の範疇に入る。化学肥料と言ってもすべて人為的に合成された化学物質とは限らないのだ。
一方、有機肥料は、動物・植物性の有機物で肥料成分(窒素・リン・カリウム)を含むもので、植物性の油粕、糠や動物性の魚粕、牛糞、鶏糞、肉骨粉などがある。有機肥料は、土壌の微生物が時間をかけて分解しながら、植物に吸収されるため、化学肥料に比べて即効性はないが、効果が長続きする。有機肥料は、土壌の微生物の働きや循環を活性化させるため、化学肥料による近代農法よりも良いイメージがあるが、必ずしもそうとは言えない一面もある。たとえば、化学肥料は悪臭やガスを発生させず、また害虫の直接的原因とならないが、未完熟の有機肥料は悪臭、ガス、病害虫の原因となる。有機肥料もよく発酵させれば、これらの問題は起きないが、肥料中に重金属を含む場合は、発酵しても除去されることなく残留し、作物に再吸収される危険性がある。一方、化学肥料の場合、重金属を含む危険性は低い。
また近年、有機農産物の人気の高まりから、良質の有機肥料を求める声が高いが、優良とされるある有機肥料のメーカーの場合でも、その原料には大手メーカーの巨大工場から廃棄される社員食堂の食料残渣や従業員の糞尿を使用している。このような場合、重金属や各種生体ホルモンや環境汚染物質が混入している可能性が大きい。その他にも、別の大手肥料会社が原料にする木材チップには、古材に塗布されていた白アリ用殺虫剤のヒ素が残留していること判明している。またホームセンターなどで売られている牛糞、鶏糞の有機肥料でも、家畜の餌に遺伝子組み換え作物や重金属が含まれていれば、分解されることなく、作物に再吸収される危険性もある。有機農法を行う場合、自家配合で堆肥を作るのでなければ、肥料の原料を厳しくチェックする必要がある。これらの危険性を避けるには、どうしたら良いか。私も市民菜園で野菜作りをしながら、いろいろな野菜作りの先生に教わってきた。ある自然農法の先生によれば、畑には一切、動物性の堆肥を入れない方が良いとのことだった。使うのは全て植物性。たとえば、汚染されていない山の腐葉土を入れたり、畑の雑草を畝の間に敷き詰め、米ぬかを撒いた上から薄めた木酢液をかけ、その土地の微生物を呼び込む方法などである。また、馬糞の場合は、餌にも遺伝子組み換えの飼料が含まれておらず、重金属汚染の心配もないため、使用しても問題ないとのことだった。私の借りている市民菜園はもともと田んぼを畑にした土地で、粘土層であるため、自然農法の実践はかなり難しい。現在は、馬糞+雑草+米ぬかの自然農法で野菜作りをしているが、上手くいくときもあれば、全く駄目なこともある。
一方、市民菜園で20年、30年と野菜作りをしているベテランのおじさんやおばさん達は、長年の経験から肥料を上手く使い分けている。彼らは、雑草や腐葉土を使うだけでなく、化学肥料や鶏糞を少量上手く使い、安定した収穫を上げている。こだわりも大切だが、肥料を上手く使い分け、安定した収量を上げることも大切だと教わった。
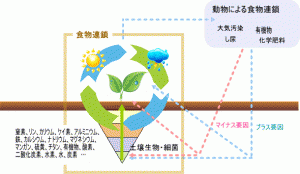
画像はこちらからお借りしました。
上記の内容をまとめると以下のことが分かります。
植物成長にとって必要なのものは窒素・リン・カリウムの3要素である。
それらの与え方として、微生物による有機物の分解作用を用いる有機農法と、成分(無機物)のみを直接与える化学農法が存在する。
化学農法は、化学肥料の大量使用から窒素化合物が土壌から大量に流出し、地球の生態系へ悪影響を与えることが懸念されており、また化学肥料で作られた農産物に含まれる栄養素の乏しさや過剰な硝酸態窒素が人体の健康面に与える恐れがある。
有機農法は、未完熟の有機肥料は悪臭、ガス、病害虫の原因となり、更に微生物は重金属を分解できない。その結果、植物に重金属が蓄積し、我々の体に吸収される危険性がある。
つまり、化学農法にしろ有機農法にしろどちらにもメリットデメリットがあり、単純に有機農法を選択すれば良い結果をもたらすとは限らない。重要なのは、その中身となる植物の成長のしくみや微生物が有機物を分解するしくみを理解した上で、現状で何が足りていないかを見極めてその状況に応じた対処していくことである。

画像はこちらからお借りしました。
一方で、記事の最後に記載されているように、化学農法と有機農法のバランスが大事となっているがどうすればその見極めができるようになるのか?や微生物が植物に与える影響は?、植物の免疫と微私物の関係は?等々は今後の課題として引き続き追及していきます!
投稿者 noublog : 2014年12月08日
TweetList

トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.new-agriculture.com/blog/2014/12/2988.html/trackback

